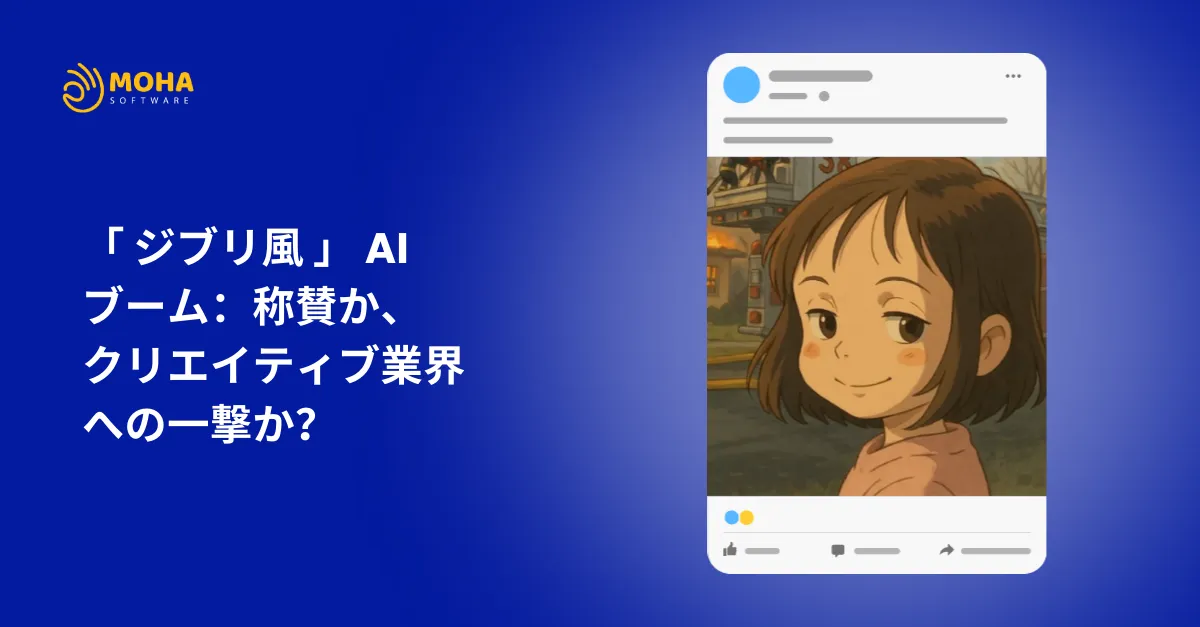TPO – 人の手によって描かれたものではないにもかかわらず、スタジオジブリの特徴を色濃く反映したアニメ風の画像が、今ソーシャルメディア上を席巻しています。スマートフォンのAIアプリやChatGPTなどを使えば、ユーザーは自分のポートレートをアニメ風に変換し、ジブリ風の風景を再現することができます。このブームは大きな反響を呼ぶ一方で、創作倫理をめぐる激しい議論も巻き起こっています。
ここ数日間にSNSを利用したことがあるなら、ジブリスタジオの代表的なスタイル ― たとえば『千と千尋の神隠し』『となりのトトロ』『ハウルの動く城』といった名作を生み出したアニメーションスタジオ ― を模倣したAI生成の画像を目にしたことがあるかもしれません。
最新のChatGPTのバージョンを使えば、有名なインターネットミームや個人写真を、スタジオジブリの創設者であり、AI技術に対して厳しい批判を繰り返してきた宮崎駿監督の独特なスタイルに変換することも可能です。
ジブリ風 AIブームをめぐる論争
このブームは、AIが著作権のある創作物を利用することに関する倫理的な懸念を呼び起こし、アーティストの未来や、人間の創造性の価値が、アルゴリズムに支配されつつある時代においてどうなるのかという問いを投げかけています。
手描きの緻密なアートスタイルと詩的な物語性で知られる宮崎駿監督は、アニメーションにおけるAIの役割に対して以前から批判的な姿勢を示してきました。
彼がAIに対して最も強く反発したシーンの一つは、2016年のドキュメンタリー『終わらない人 宮崎駿』の中で描かれています。
この映画の中で、プログラマーのグループがAIによって生成されたアニメーションのデモ映像を宮崎監督に見せました。映像には、ゾンビのような生き物が地面を這いずりながら、頭で体を引きずって進む様子が描かれており、「人間の想像を超えた動き」だと開発者たちは説明しました。
しかし、それを見た宮崎監督はこう語りました。
「以前、毎朝会っていた障がいを持つ友人がいます。彼にとって、手を上げてハイタッチをすることすら困難なことでした。腕の筋肉が硬直して、私の手に届かなかった。今、その友人のことを思い出すと、こんなものを見て面白いとは到底思えません」。
彼はさらにこう続けました。「これを作った人たちは、“痛み”というものをまったく理解していない。私は本当に嫌悪感を覚える……これは“生命”への冒涜だと感じる」。
ジブリ風のAI画像の魅力は否定できません。ほんの数回のクリックで、まるで名作の中に入り込んだような幻想的で美しいアニメ画が手に入るのです。しかし、その美しさの裏には「AIは芸術を称えているのか?それとも他人の努力を盗んでいるだけなのか?」という根本的な問いが潜んでいます。
このAIトレンドはSNSを中心に広まり、ついにはホワイトハウスまでもが3月27日にこのブームに参加しました。彼らが投稿したAI画像は、ドミニカ共和国出身の36歳女性が米国移民税関捜査局(ICE)に逮捕された直後に涙を流している様子を描いたもので、激しい批判を浴びました。
その画像はX(旧Twitter)上で4,500万回以上の閲覧数を記録し、「恐ろしい」「非情すぎる」といったコメントが殺到しました。
スタジオジブリにインスパイアされたAI作品が物議を醸すのは、これが初めてではありません。
昨年10月、1997年の名作『もののけ姫』をAIが再現したトレーラー動画がSNSでバズり、大きな反発を招きました。
このAIトレーラーでは、ビリー・クラダップ、クレア・デインズ、ミニー・ドライヴァーなどオリジナルの英語吹き替え声優の音声を使い、手描きアニメーションの全てを実写風のCGIに変換していました。
人工知能と目に見えない模倣の問題
AIは単なるツールに過ぎず、芸術をより多くの人に届ける手段だと考える人も少なくありません。しかし問題は、AIがどのように機能しているかにあります。AIのアルゴリズムは、何百万もの既存の画像から学習しており、その中にはジブリ作品のような著作権のある作品も含まれています。これらは作者の許可やクレジットなしに使用されており、深刻な著作権侵害やクリエイターの権利の問題を引き起こしています。
多くのアーティストが、自分のスタイルを模倣したAI作品が本人の関与なく生成されることに強い不満を表明しています。これらの作品は、人間と機械の境界を曖昧にするだけでなく、芸術の本質的な価値そのものに疑問を投げかけています。
画像生成分野におけるAIの急速な発展は、アーティスト個人だけでなく、アニメ業界全体をも脅かしています。たとえば、制作会社が安価に「ジブリ風」のイラストをAIで生成できるようになれば、多くのイラストレーターが職を失う可能性もあります。
多くの専門家は、AIの乱用が才能の衰退を招くと警鐘を鳴らしています。研究者トリスタン・S・ゴーツェは、AIによるアート生成は「労働の窃盗」であると指摘。「AIが創造するアートは、搾取と搾取による労働の盗用だ」と強く非難しています。
著名なイラストレーターであり、AI企業に対する集団訴訟の原告の一人であるカーラ・オルティス氏は、アーティストの許可なく作品をAIの学習に利用することは権利侵害だとし、「これらのモデルは私たちの作品を無断で使用しているだけでなく、創作活動の価値そのものを損ない、努力なしにコピー可能なものにしてしまっている」と訴えています。
欧米では現在、多くのアーティストや団体が、AIの芸術利用に関する明確なルール作りを求めて声を上げています。特に、アメリカのアートコンテストでAIが生成した作品が優勝したことを受け、議論がさらに加熱しました。アメリカ美術家協会は、AIプラットフォームに対し、学習に使用したデータソースの公開を求めるなど、オリジナルのコンテンツ制作者の権利保護に向けて動いています。

多くの観客は「AIは美しい画像を生み出すことはできても、芸術の“魂”までは再現できない」と語っています。ジブリの絵は、単なる柔らかな線や色彩だけではなく、そこには息遣いや哲学、そして人間が長い年月をかけて築いてきた文化が宿っています。
ある視聴者はこう語っています。「AIの進化は避けられない。しかし、それが芸術を破壊するものになるのではなく、倫理的かつ公正に活用する方法を私たちは模索すべきです。芸術とは本来、創造そのものであり、本物の創造性は機械からは生まれないのです」。
ブームが引き起こしたシステム過負荷の現実
強力な新しいAIモデル、無料アクセスの提供、そして「ジブリ風AI画像ブーム」が重なり、まさに“完璧な嵐”が巻き起こりました。OpenAIのCEOサム・アルトマン氏は、ChatGPTが1時間で100万人の新規ユーザーを記録した瞬間があったことを明かし、2年前には同じ数を達成するのに5日かかっていたことと比べても、驚異的なスピードです。
市場調査会社SensorTowerのデータも、このAIブームの影響を裏付けています。アプリのダウンロード数、週次アクティブユーザー数、収益のすべてで記録を更新し、それぞれ週次で11%、5%、6%の成長、前年比では500%以上の伸びを示しました。さらに、Similarwebの統計によると、ChatGPTは2024年3月のわずか28日間で40億回以上のアクセスを記録し、初の大台を突破しています。
しかし、このような爆発的な成長の裏には、深刻なインフラ課題が隠れています。アルトマン氏は自身のX(旧Twitter)アカウントで、システム過負荷の現状を率直に共有し、画像生成機能の一時的な制限を導入したことを発表しました。「画像生成リクエストの一部は拒否される可能性がある」との警告とともに、技術チームが対応に奔走していることを明かしました。
事態が最も深刻化したのは4月1日。アルトマン氏は「OpenAIは現在、容量の課題に直面しており、新機能のリリースが遅れる可能性がある。また、サービスの遅延や不具合が発生することも考えられる」と公式に認めました。
ChatGPTのこの急成長は、生成AIの計り知れない魅力を改めて浮き彫りにすると同時に、インフラやスケーラビリティ(拡張性)という根本的な課題も浮き彫りにしています。SNS上の一時的なトレンドが、世界屈指のAI企業のシステムを揺るがすほどの影響力を持つ今、AI産業がまだ“過熱気味の発展途上”であることは明らかです。今後、処理能力や運用体制の整備が、業界全体の持続可能な成長に向けた鍵となるでしょう。